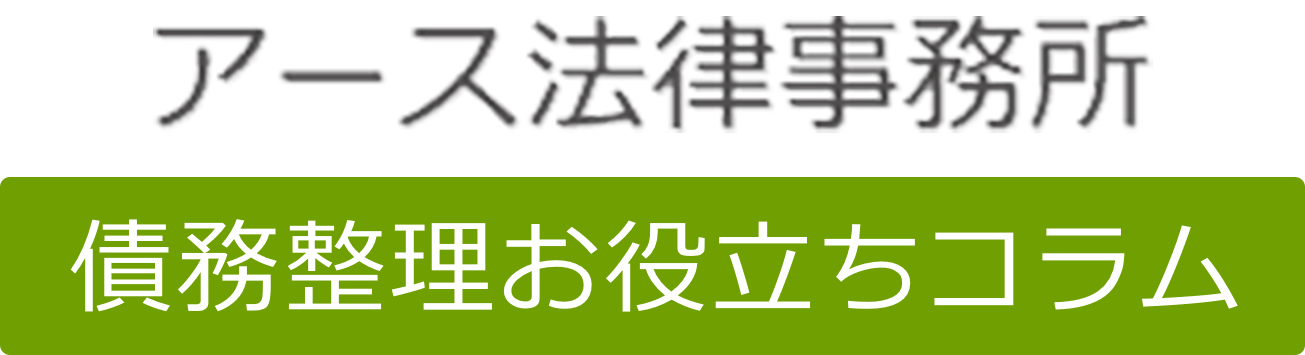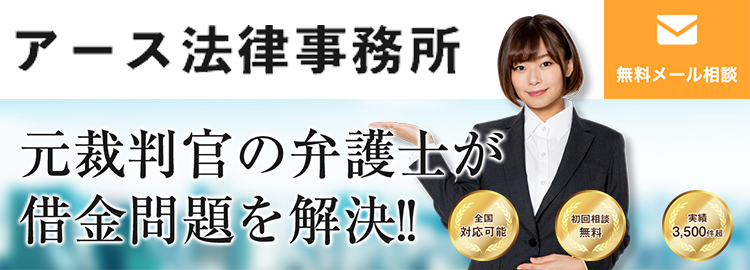自己破産後に貯金をするタイミングと注意点
自己破産の際、破産手続開始決定が出た後に得たお金は原則として手元に残せます。また、破産手続開始決定が出る前に得たお金も、現金99万円までは手元に残すことができます。もっとも、「現金99万円まで」というルールは、具体的には裁判所によって運用が異なるため注意が必要です。自己破産後に貯金ができるようになるタイミングや注意点についてまとめました。
目次
自己破産後貯金は可能なのか?

破産手続開始決定後に取得したお金や財産は裁判所によって処分されないので、貯金が可能です。破産手続開始決定前に得た財産でも、99万円までの現金は手元に残しておけます。
【自己破産手続開始前】
自己破産手続開始前であっても、現金は99万円までであれば、原則として手元に残せます。ただし、99万円を超える財産を持っていた場合、超過した分については裁判所が処分し債権者に配当します。
なお、「現金99万円まで」というルールにはいくつか注意点がありますので、後程詳しく解説します。
自己破産後に貯金をするためには、まず自己破産の手続きを滞りなく進め、免責許可を受けることが大切です。「免責」とは、借金がゼロになる制度のことで、基本的には裁判所の指示に従って正直かつ誠実に手続きを行えば、免責許可を受けることができます。
【自己破産手続後】
自己破産が終われば、以後、財産の所有に制限を受けることはありません。借金の支払いから解放されますので、自己破産以後はお金をためやすくなるでしょう。
自己破産をすると、その後5-7年ほどの間、新たな借金やクレジットカードの作成・利用、分割払いが難しくなります。そのため、自動車やスマートフォンなどを買う際は、一括払いでの購入になります。そのため、自己破産後は貯金することが大切になります。
自己破産手続開始決定が出た後に得た財産は処分されない
自己破産の際の財産の扱いについては、「破産手続開始決定」が出るかどうかが重要です。破産手続開始決定が出る前に入手した財産は、金額によっては裁判所に処分されてしまいますが、破産手続開始決定後に手に入れた財産は、原則として金額にかかわらず自分のものにすることができます。
【破産手続開始決定とは】
破産手続開始決定とは、裁判所に自己破産を申し立てた結果、自己破産の手続きが開始されることを言います。かつては「破産宣告」と言っていましたが、現行法では「破産手続開始決定」が正しい言い方です。
破産手続開始決定が出ると、以後申立人は「破産者」となり、免責許可が出るまでは一部の資格職に就けなくなるなど、様々な効果が生じます。
破産者に財産がある場合、「管財事件」という種類の手続きになり、破産管財人という破産手続きのプロが選任されます。破産管財人は財産を管理・処分して債権者に配当しますが、その対象となる財産を「破産財団」と言います。
債務者の財産が破産財団に入るかどうかは、「破産手続開始決定の前に手に入れたか、後に手に入れたか」が基準となります。原則として、破産手続開始決定前に入手した財産が処分の対象になります。
破産手続開始決定は申立て後すぐに出るわけではなく、日弁連が実施した「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告編】(https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/books/data/2020/2020_hasan_kojinsaisei_1.pdf)」によれば、同時廃止事件における破産申立から破産開始決定までの平均日数は,39.28日と、約40日ほどかかっています。
破産手続開始決定が出れば、原則としてその後は財産を自由に手に入れ、処分することができます。宝くじに当たっても、高額の遺産を相続しても問題ありません。
自己破産手続開始後、貯金ができるようになるタイミング
自己破産手続開始決定が出た後、生活や将来のために貯金ができるようになるのは、基本的には免責許可決定が下りてからになります。以下に自己破産手続きの流れに沿って紹介します。
(1)弁護士に依頼~自己破産申立て前
自己破産を弁護士に依頼すると、借金の督促が止まります。それまで返済に充てていたお金については、自己破産の際の裁判所費用(予納金)や弁護士費用等のために積立てを行うことになります。
弁護士が正式に契約を結ぶと、即座に各債権者に「受任通知」を発します。この受任通知には債務者に直接の取り立てや連絡を禁止する効果があり、債務者は借金の支払いから解放されます。
なお、返済しなくて済むようになったお金については、税金を支払ったり、生活に必要不可欠な出費に回すことも可能ですが、特定の債権者に弁済したりすると後で問題になります。弁護士の助言に従って使うようにしましよう。
(2) 破産手続開始決定~免責許可決定まで
破産手続開始決定が出るとともに、自己破産手続が「同時廃止」になるか、「管財事件」になるかが決まります。
自己破産には、大きく分けて、「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、裁判所がどちらになるかを決定します。
同時廃止
処分対象となる財産がない人向けの手続きで、破産管財人が選任されない、簡易でスピーディーな手続きです。同時廃止になった場合は、財産の処分は行われません。
管財事件
処分すべき財産がある人や、裁判所が詳しい調査が必要だと判断した人向けの手続きで、破産管財人が選任されます。
管財事件となった場合、99万円を超える現金など、処分対象になる財産がある場合は、破産管財人が財産の管理や処分、清算を行います。
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定から免責決定までの平均日数は、先述した日弁連実施の2020年の調査によると、68.12日となっています。管財事件になった場合はこれよりも長くかかります。
(3)免責許可決定が出て以降
免責許可決定が出れば、自己破産手続きが無事終了したことになり、以後、本格的に今後の生活のためにお金を貯めることができるようになります。
自己破産をすると、その後5~7年ほどの間、以下のことが難しくなります。
- 新たなローンや借金への申し込み
- クレジットカードの新規作成や利用、更新
- 分割払いでの商品購入
その理由は、日本には「信用情報機関」という、個人のお金の貸し借りなどの信用情報を記録する機関があり、この記録に5~7年間、自己破産の記録が記載されるからです。これを俗に「ブラックリスト入り」と言います。
金融機関や貸金業者、カード会社は信用情報機関の記録をもとに審査を行うため、ブラックリスト入りしていると審査に落ちてしまいます。
5~7年経過すると、自己破産の記録は消え、再び借金やクレジットカードの利用等ができるようになります。
【クレジットカードの代替手段】
近年は、オンラインショッピングにて、決済方法が「クレジットカード払いのみ」という店も増えています。こうした場合でもクレジットカードの代用品として使えるのが「デビットカード」です。
デビットカードは銀行口座と紐づけされており、商品やサービスを購入すると銀行口座に入っているお金の分だけ即座に引き落としされる仕組みです。お金を借りることが無いので、契約の際に信用情報が閲覧されることはありません。銀行口座に、買いたい商品・サービス以上のお金が入っていないと使えないカードなので、こまめな貯蓄が重要になってきます。
また、一定金額のお金をチャージする形式のプリペイドカードにも、クレジットカードと同様に使用できるものがあります。
自己破産をすると決済方法が限定されるため、不便なこともありますが、現実に持っている以上のお金を使わない生活をすることで、貯金がしやすくなるでしょう。
手元に残せる現金はどれくらいか
自己破産手続を取っても、99万円以下の現金は原則として手元に残すことができます。ただし、財産を具体的にどのような基準で取り扱うかは裁判所によっても異なります。以下は基本的に東京地裁における基準をご紹介します。
自己破産をしても手元に残せる財産のことを「自由財産」と言い、以下のものがあります。
(1)新得財産
破産手続開始後に新たに手に入れた財産のことです。
(2)差押禁止財産
家財道具など生活に必要な物品が当てはまります。
(3)99万円以下の現金
原則として、現金は99万円までであれば手元に残せます。
ただし、このルールには注意点があります。
①預貯金の取り扱い
預貯金は現金とは別の財産に分類され、20万円までであれば手元に残せます。
複数口座がある場合は全ての口座を合計して20万円までとなります。
預貯金以外の財産も、20万円以下であれば原則として手元に残すことができます。
②現金が33万円以上あると管財事件になる
「99万円までの現金は手元に残せる」というルールがあるものの、現金が33万円以上ある場合は、財産がある人向けの手続きである「管財事件」になります。
この2種類の手続きは、主に費用面で大きな差があります。
「同時廃止」になった場合、裁判所費用(予納金)は2万円程度で済みます。ところが、「管財事件」になると、裁判所費用は最低でも20万円以上かかります。
つまり、例えば33万円を何万円か超えるくらいの現金をもったまま自己破産をすると、費用面でかなり損をするおそれがあるのです。
同時廃止になるか、管財事件になるかはかなり重要な違いですので、事前に弁護士に相談してアドバイスを受けられることをお勧めします。
③自由財産の拡張範囲は裁判所によって異なる
東京地裁以外で自己破産をする場合、「現金とほかの財産を合わせて99万円まで」という運用をしている裁判所もあるので、注意が必要です。例えば預貯金が18万円ある場合、残せる現金は「99万―18万=71万円」となります。
「現金とほかの財産を合わせて99万円まで」という運用の場合、裁判所にもよりますが、99万円の範囲内であれば比較的緩やかに財産の所持を認めるケースがあります。個別の裁判所の運用については、具体的には弁護士にお尋ねください
破産開始手続開始決定までに受け取ったもの
破産手続開始前に受け取った給与やボーナスなどは、現金の形で所持していれば99万円まで残すことができます。預貯金の形で持っていた場合は、合計20万円以下であれば手元に残せます。
これを超える金額の財産については、破産管財人が管理し、必要な場合は換金し、債権者に配当します。
破産手続開始決定の時点で「同時廃止」となった場合は、財産を処分される心配はありません。
破産開始手続開始決定後に受け取ったもの
破産手続開始決定後に受け取った財産は、「新得財産」として扱われ、原則として金額に関係なく自由に取得し保有することができます。
ただし、お金を借りた先が銀行や信用金庫で、その金融機関の口座に給与などが振り込まれた場合は、自己破産をすると給与口座が凍結されることがあります。
弁護士に依頼していれば事前に指示があると思いますが、あらかじめ勤め先に頼んで振込先を変更しておくなど、対策をしておきましょう。
なるべく早く破産手続開始決定を出す方法
親の体調が悪く近い将来の相続が予想される場合など、なるべく早く破産手続開始決定が出て欲しい場合は、事前に弁護士に相談しましょう。
ご自身が破産を申し立てる予定の裁判所が東京地裁ならば、「即日面接」という制度が利用できます。これは、自己破産を申立てた当日か、遅くとも3日以内に、代理人である弁護士と裁判官が面接を行い、面接当日の午後5時付けで破産手続開始決定を出します。
即日面接は、代理人の弁護士への信頼を前提する制度で、事前に申立人に対して十分な調査を行っていることが重要です。依頼した弁護士と綿密な打ち合わせをして、スピーディーな破産手続開始決定につなげましょう。
参考サイト:「裁判所 東京地方裁判所 民事第20部(倒産部) 5.よくある質問(https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section20/situmonn_tousannbu/index.html)」
東京地裁以外でも、弁護士に自己破産を依頼すると、申立書類の不備を減らせるなどのメリットがあり、全体的に迅速に手続きを進められます。
自己破産時に預金隠しをしてはいけない
財産隠しをしたり、裁判所に嘘をついたりした場合、免責が不許可になることがあります。免責不許可になると借金がそのまま残るため、非常に深刻な事態になります。
管財事件で選任される破産管財人は、債務者の財産を調査する権限を持っています。破産管財人は破産手続に詳しいプロの弁護士で、預金通帳の不自然な動きなどにはすぐ気が付きます。合理的な説明ができない場合、財産隠しを疑われ、最悪の場合は免責不許可となります。
「99万円を超えるお金を持っているけど、裁判所にとられるくらいなら、何とか隠したい」とお考えになる方もいることでしょう。しかし、隠匿が発覚するととても困ったことになるため、財産状況は正直に申告しましょう。
この記事の監修者

-
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑