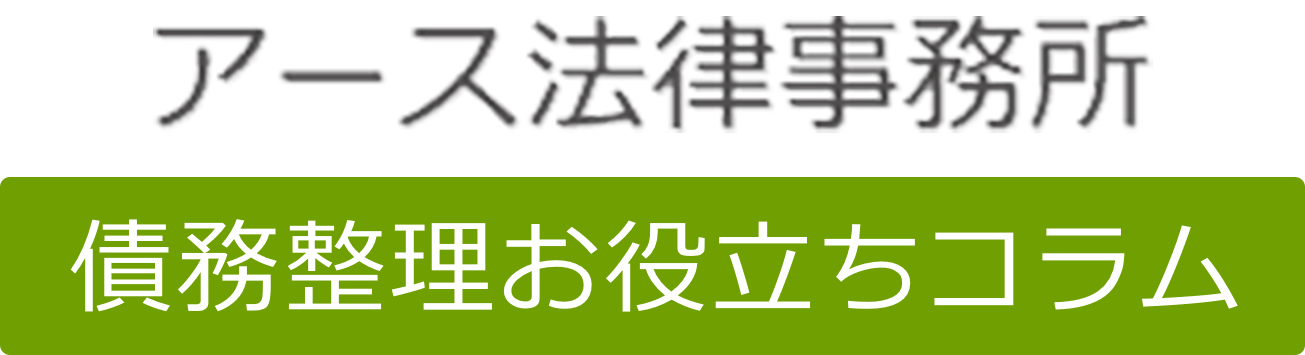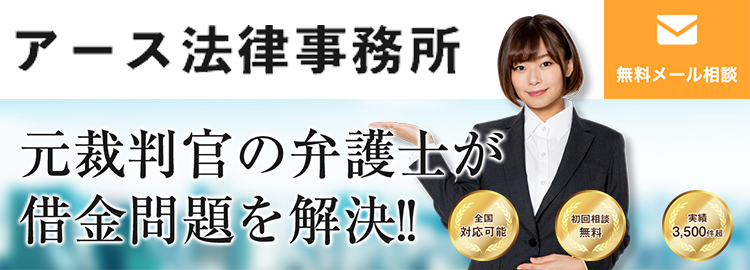任意整理手続きの流れと必要な期間の目安
任意整理の流れと、手続きにかかる期間についてまとめました。裁判所を通さない私的な交渉である任意整理は、比較的手間のかからない手続きです。まず専門家へ相談し、契約、費用支払い、調査、和解交渉、和解成立と続きます。和解成立後から完済までの期間は3~5年、新規の借り入れが難しくなるブラックリスト期間は完済から5年で終了します。
目次
任意整理の流れと手続に必要な期間

任意整理は、弁護士に依頼して私的に債権者と交渉する手続きなので、裁判所で行う個人再生や自己破産のように複雑な手続きではなく、依頼後に借金をした本人(債務者)がするべきことは多くありません。任意整理に必要な期間は3~6ヵ月程度、和解後の返済期間は3~5年程度となっています。
することが無いと逆に不安になるかもしれませんが、多くの事務所では、弁護士が定期的に報告の連絡をくれるので心配しなくて大丈夫です。
任意整理の主な流れは以下のようになっています。
- 専門家への相談予約
- 相談と契約
- 手続費用の支払い
- 調査票作成
- 和解案作成
- 和解交渉
以下、具体的に解説していきます。
専門家への相談予約
まず、専門家にコンタクトをとります。電話か、法律事務所のホームページの相談フォームから問い合わせ、実際に会って相談する日を決めるのが一般的です。近年は、債務整理に関しては多くの法律事務所が無料で相談に応じているので、気楽に相談できます。
専門家の選び方としては、友人や身内から評判の良い弁護士の情報があれば確実です。特につてがない場合、実際にコミュニケーションをとってみて相談しやすい雰囲気の事務所・専門家を選ぶと良いでしょう。
複数の法律事務所に相談して、よさそうな事務所を選んで契約することも問題ありませんので、違和感や気になる点がないか、この時点で確認しておきましょう。
相談と契約
任意整理の場合、専門家と実際に対面して話すのはこれが最初で最後という場合も多いので、質問事項を事前にメモして持っていくのも良いでしょう。
相談の際は、借金に関することは全て包み隠さず正直に説明します。友人からの個人的な借金や、連帯保証人がいる債務など、今回の任意整理で減額対象とすることを望まない借金についても、その存在を説明する必要があります。借金の全体像が明らかでないと、専門家は相談者の状況にあったアドバイスができないからです。
任意整理のデメリットや、正式に依頼した場合の弁護士費用、支払い方法などについても、相談の時点で確認しておきます。
【必要な持ち物】
相談時には、借金の残高や返済期間、債権者(お金を貸した金融機関や貸金業者等)の数が確認できる資料を可能な限り持っていきます。例えば、以下のものがあります。
- 借入の利用明細書
- 請求書
- 契約書
- 利用しているクレジットカードやキャッシングカード
これらの書類を紛失して、全ての借金について明確に記憶や資料がなくても、調査が可能な場合があります。その場合は、その旨を正直に伝えましょう。
また、債権者から訴訟を起こされ、裁判所からの通知が届いている場合は必ず伝えてください。早急に対応しなければならないケースがあるからです。
それ以外の持ち物としては、身分証と契約をする場合の印鑑(認印可)を持っていきます。ケースによっては、弁護士からこれ以外の書類の提出を求められることがあります。
【契約の締結】
相談内容や弁護士の雰囲気に納得がいったら、正式に契約書に署名して依頼します。契約書の内容で不明点があれば積極的に聞いて確認しておきましょう。
正式に契約を結ぶと、弁護士は即日から3日以内に、借金整理の対象とした各債権者に「受任通知」を発します。この通知には、弁護士が任意整理を受任した旨と、以後、債務者と直接連絡を取らないように要請する文面が記載されています。既に借金の返済が滞って督促が届いている場合、この受任通知でストップできます。
契約締結から1週間経っても、まだ債権者から督促が届く場合、弁護士に相談しましょう。
手続費用の支払い
契約をしたら費用の支払いをします。費用はできれば一括での支払いが望ましいといえます。その理由は、通常、費用の支払いが完了しないと和解交渉が進められないからです。
もっとも、任意整理を依頼する時点で、お金に困っているわけですから、依頼の時点で全額用意できなくても大丈夫です。その場合は、分割払いになりますが、やはりできるだけ分割回数が少ないほうが借金問題の早期解決につながります。
任意整理にかける時間が長引くと、債権者から訴訟を起こされるリスクが高まります。また、手続きの見通しが立てやすくなるので、可能な限り早めに支払うことをお勧めします。
調査票作成
弁護士は各債権者に受任通知を発すると同時に、任意整理に必要な書類を取り寄せます。特に重要なのは、現在の債務額や取引状況を記した「債権調査票」で、弁護士はこの金額をもとに、現実的な和解案を考えます。
また、クレジットカードのキャッシングを長期にわたって利用しているケースなど、過払い金が発生している可能性がある場合は、取引履歴に基づいて引き直し計算を行います。
これらの調査には1~3ヶ月程度かかります。
和解案作成
調査により正確な借金の額が確定すると、これをもとに、依頼者と弁護士で和解案(減額の内容と、リスケジュールした返済計画案)を作成します。通常は返済期間は3~5年程度で、無理のない返済プランを考えます。
和解交渉
和解案をもとに弁護士と債権者が話し合って交渉します。交渉には通常、3ヶ月程度を要しますが、債権者によっては和解に応じずに、交渉が長引くことがあります。通常は、債務者本人は話し合いには参加しません。
債権者が和解案に合意すれば、和解成立となり、その日のうちに合意書を取り交わします。和解が成立すれば任意整理は完了となり、その後は返済計画に従った分割払いがスタートします。
和解成立までに必要な機関は、債権者数や事案にもよりますが、概ね3~6ヵ月程度となっています。
任意整理の和解成立後の完済までの期間
和解が成立した後、分割払いで借金を返済する期間は通常3~5年程度となっています。債務額が少ない場合や、収入が多い場合などは3年未満での返済を求められることもあります。
和解条件は債権者によりますが、消費者金融の場合は厳しめで、利用年数が1年未満だと1年の分割払い、3年の利用だと3年というケースもあります。逆に、クレジットカード会社の場合は気長で、7年払いや8年払いに応じてくれるケースもあります。銀行のカードローンの場合は、保証会社がどこかによって異なってきます。
任意整理の経験が多い法律事務所の場合、どの会社は短めで、どの会社は長期間待ってくれるなど、交渉結果の蓄積がありますので、事前に聞いてみても良いでしょう。
手続き中の注意点
裁判所を通さない任意整理では、手続き中に依頼者がやるべきことは少ないのですが、いくつか注意点があります。以下に詳しく解説します。
和解成立後に支払い条件の変更は原則としてできない
任意整理で債権者との和解が成立してからは、和解契約書に記載された支払い条件を後から変更することは基本的にできません。例えば、「支払い期間3年で和解したけれど、やっぱり苦しいから5年にしてほしい」と、後から変えてもらうのは難しいと考えてください。
任意整理の場合は、個人再生や自己破産と違って家計簿の作成・提出を求められることはありませんが、自分の収入や支出の状況を客観的に見て、無理のない返済計画を考え、それに沿って和解案を考えることが大切です。
例外的に、債権者は早く返済する分には文句は言いませんので、ボーナスや昇給などを利用して繰り上げ返済を行い、早期に借金問題を終結させることは可能です。
繰り上げ返済が可能な場合、弁護士に依頼して債権者と交渉すれば、返済総額を減額してもらえる可能性もあります。早期返済を希望する場合はあらかじめ弁護士に相談されたほうがいいでしょう。
もっとも、収入に大きな変化がないのに無理をして早期返済をすることは、生活が苦しくなるなどのデメリットもあるので、慎重に行ってください。
任意整理開始から借金の返済が終わるまでは追加の借金はしない
任意整理手続を開始してから、借金返済が完了するまでは、追加の借金はしないようにしてください。
任意整理をすると5年前後、信用情報機関に任意整理の記録が残ります。これを俗にブラックリスト入りと言い、記録が残っているうちは新たな借金やローンが組めなくなります。
クレジットカードも原則として使えなくなりますが、カード会社によって信用情報機関の記録を確認する頻度はまちまちなので、カードによってはしばらく使い続けられることがあります。カードのキャッシング機能を使えば、現金を引き出すことも可能です。
しかし、せっかく任意整理で借金を減額したのに、また新たに借金をすることで返済のペースが狂い、最悪、返済できなくなる可能性もあります。
任意整理した借金をすべて支払い終えるまでは、新たな借金をしないでください。
任意整理後の返済は遅れずに行う
任意整理後の返済は、遅滞なく行うよう心掛けてください。任意整理後に2回以上滞納すると、債権者が待ってくれなくなり、借金残額を一括請求される可能性があります。
急病や会社の倒産など、事情があってどうしても返済が困難な場合は、できるだけ早めに弁護士に相談してください。基本的には自己破産など、裁判所を通じた手続きをとることになります。
任意整理後、何年経てば新たな借金ができる?
任意整理をすることにより、新たな借金ができなくなる期間は、手続き後に借金を完済してから5年です。例えば、3年の分割払いで和解して、約束通り返済し終えた後、5年間は任意整理の記録が残っていますので、合計8年間は新たな借金ができません。
信用情報機関とは、日本に3つある、個人の信用情報を記録し保管する団体です。日本の金融機関や貸金業者は、3つの信用情報機関いずれかに加盟して、新たにお金を融資したり、クレジットカードや分割払いの契約を申し込まれたりしたときは、信用情報機関の記録を参照します。
任意整理の記録とは、すなわち、返済に困って債権者に減額してもらった記録のことですので、新たに融資する企業にとってはマイナスの情報です。このようなマイナスの情報を「事故情報」と言います。これが残っているうちは、融資の際の審査に落ちる可能性が高いのです。
もっとも、信用情報機関はずっと事故情報を残しておくわけではなく、5年間過ぎれば記録が消えます。記録が無くなれば以前のように借金やクレジットカードの利用が可能です。
3社の信用情報機関には、本人が問い合わせれば1000円~2000円程度の手数料で記録の履歴を公開してくれます。
【日本の信用情報機関】
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
・全国銀行個人信用情報センター
JICCとCICは指定信用情報機関と言って、内閣総理大臣から指定を受けた信用情報提供を行う法人です。大切な個人情報を扱うことから、業務を適切・安全的に行うことが求められており、加盟企業であっても信用情報を目的外の理由で閲覧したり、利用したりすることはできません。
3社は情報を共有しています。例えば、「消費者金融相手に任意整理したから、銀行カードローンなら大丈夫だろう」と申し込んでも、銀行系の「全国銀行個人信用情報センター」にも任意整理の情報が共有されているため、審査に通ることは難しいのです。
任意整理後、2回目の任意整理はできる?
任意整理をした後に2回目の任意整理をすることは可能です。任意整理は裁判外の手続きで、特に法律上の回数制限も存在しないので、原則として何度でも行うことができます。
ただし、債権者が1回目と同じ場合、和解条件が1回目より厳しくなる可能性が高いことには注意してください。債権者によっては、和解できずに裁判になる場合もあります。和解が難しい相手の場合は、個人再生や自己破産と言った裁判所を通した手続きを検討することになります。
2回目の債権者が1回目とは違う債権者の場合、和解条件が特に厳しくなるなどの影響は出ないでしょう。例えば、以下のような場合です。
- 1回目で任意整理の対象としなかった債権者
- 1回目の任意整理の後、新たな借金ができるようになってからした借金の債権者
2回目の債務整理で不安な点がある場合は、積極的に弁護士に問い合わせて、解消されることをお勧めします。
この記事の監修者

-
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑