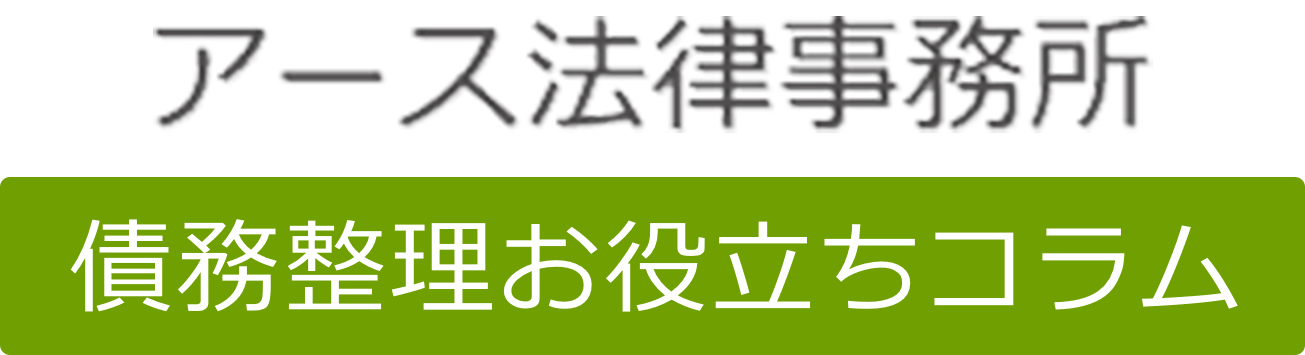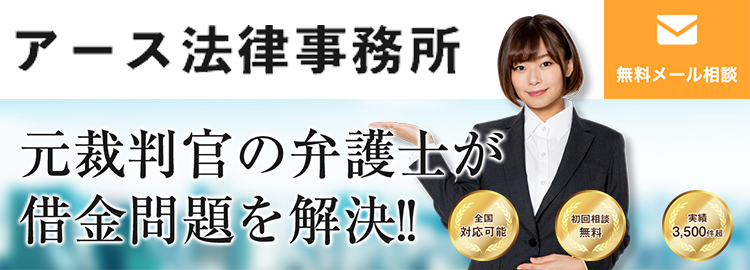過払い金の返還金額の目安について
過払い金がいくら戻ってくるか、金額の目安について概説します。過払い金の額は借金した時の利率や借金額、返済期間によって変わりますが、目安としては50万円を29%の利率で借りて5年で返済した場合、50万円以上の過払い金が発生している可能性があります。
過払い金が戻ってくる確率や発生条件、少額の過払い金しか発生しないケース、過払い金返還請求にかかる弁護士費用についてまとめました。
目次
過払い金が戻ってくる確率や発生条件とは

過払い金は全ての借金に発生するわけではなく、取り戻すためには3つの条件を満たす必要があります。
【過払い金が請求できる条件】
(1)2010年6月以前に借り入れている
(2)グレーゾーン金利で借りている
(3)完済した日から10年経っていない
以下、「なぜ、過払い金が請求できるのか」を簡単にまとめたうえで、具体的に3つの条件について見ていきましょう。
【過払い金請求の基本】
過払い金請求は、過去に返済した借金のうち、利息制限法に定めた上限利率よりも多く支払った利息分の返還を求める手続きです。
2010年6月以前は、借金の上限金利につき、利息制限法と出資法という二つの法律が、それぞれ別々の規則を定めていました。
利息制限法の上限金利は、以下の通りです。
借金元本が10万円未満:20%
借金元本が10万円~100万円未満:18%
借金元本が100万円以上:15%
これに対し、出資法の上限金利は一律で29%でした。
「利息制限法違反だが、出資法の範囲内の金利」のことを「グレーゾーン金利」と言います。過去にグレーゾーン金利でお金を借りて返済していた場合に、払いすぎた利息は過払い金として取り返せます。
2010年6月に、法律の改正によってグレーゾーン金利はなくなりました。
(1)2010年6月以前に借り入れている
各企業がグレーゾーン金利でお金を貸していたのは遅くとも2010年6月までで、それ以降は法改正により、過払い金は発生していません。
もっとも、2006年1月にグレーゾーン金利に関する最高裁判決が出て以降、各企業は段階的に金利を引き下げているので、2007年~2010年6月までの取引については、過払い金が発生していない可能性があります。
この時期にお金を借りていた場合でも、取引履歴を取り寄せて過払い金発生の有無を調べることができますので、心当たりがある方は一度調査されることをお勧めします。
(2)グレーゾーン金利で借りている
グレーゾーン金利でお金を貸していたのは、主に消費者金融やクレジットカード会社のキャッシング枠利用で、銀行や信用金庫、住宅ローン、奨学金などは当時から利息制限法の金利を守っていました。
また、一部の消費者金融は、当時から利息制限法の範囲でお金を貸していました。具体的にはモビットやアットローン、キャッシュワン等があります。
これらの金融機関からの借金については、過払い金を請求することはできません。
(3)完済した日から10年経っていない
過払い金の請求権は、借金を最後に返済した日から10年経つと時効で消滅します。(1)(2)の条件に当てはまっていても、時効が完成すると過払い金は取り返せないので、請求は早めに行いましょう。
ただし、同じ企業相手に長期にわたって借り入れと返済を繰り返していた場合は、時効が伸びる可能性があります。
もちろん、当時借りたお金をまだ返済し続けている場合は、時効にはなりません。
過払い金の目安はいくらくらい?
過払い金の金額はお金を借りた際の利率や、借金の額、返済にかけた期間によって異なりますが、50万円を利息29%で借り、5年かけて返済した場合、50万円以上の過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、(1)利率が高い、(2)借りた金額が多い、(3)返済期間が長い、この条件に1つ以上当てはまる場合、高額の過払い金が発生している可能性があります。
まず、過払い金の計算方法をご紹介してから、具体的に条件をみていきましょう。
過払い金の計算方法
過払い金は、以下の計算式で求めることができます。
【事例】利息29%で100万円を借り入れた場合
グレーゾーン金利での利息額(1か月) : 100万×29%÷365日×30日=23,835円
利息制限法の上限利率での利息額(1か月) : 100万×15%÷365日×30日=12,328円
1か月の過払い金額 : 11,917円-7,397円=11,507円
従って、1年で完済した場合は、単純計算すると11,507円の12ヶ月分で、少なくとも13万8,000円程度が発生していることになります。
もっとも、過払い金の計算ルールはもう少し複雑です。
毎月発生した過払い金をその時点で残っている借入金の元金に充当したものとして計算します。翌月分は、元本から前月の過払い金の額を差し引いた金額に、利息制限法上限の15%の金利をかけて計算していきます。
その結果、元金は毎月どんどん減っていき、差額は元金を同額で計算した場合より大きくなります。つまり、過払い金は単純に計算した結果よりも高額になります。
(1)利率が高い
グレーゾーン金利時代の出資法の上限である29%で借りていた場合は、過払い金の金額も高くなります。
(2)借りた金額が多い
利息制限法では、借りた金額が多いほど、利率の上限が低くなるよう設定されています。
例えば、借金額が50万円の場合、利息制限法所定の上限金利は18%で、出資法上限の29%で借りていたのであれば11%分が過払い金となります。
これに対し、借金額が100万円以上であれば、利息制限法の上限金利は15%で、29%で借りていたのであれば14%分が過払い金となります。つまり、それだけ多くの過払い金が発生しています。
仮に、限度額30万円を10年利用した場合と、限度額100万円を6年かけて利用した場合では、同じ利率であれば、100万円を借りたほうが多くの過払い金が発生します。
(3)返済期間が長い
借りた金額が50万円であっても、利率29%で、3年で完済した場合は20~30万円程度、5年で完済した場合は50万円以上の過払い金が発生している可能性があります。
過払い金の計算は自分でできる?
上記のように、計算式や計算方法は公開されており、ネット上には過払い金を自分で計算できるシミュレーターも数多く存在します。しかし、複雑なことや、法的論点が絡むことにより計算式を変えなればいけないケースもありますので、弁護士や司法書士に頼んで計算してもらうことをお勧めします。
特に、複数の消費者金融と取引していたり、特定の業者から繰り返し借り入れていたりした場合は、自分で計算するのは困難です。
過払い金シミュレーターは、あくまで過払い金の有無や金額の目安を知るために利用し、正確な金額は専門家に頼んで算出してもらいましょう。
不正確な金額の過払い金を請求すると、相手企業から支払いを拒まれたり、実際に請求できる金額より過少に請求してしまったりするなど、損をする可能性があります。
過払い金は全額取り戻せる?
過払い金を100%取り戻すことは難しく、お金を借りた相手企業の態度や、交渉によるか裁判を起こすかによっても返還率は異なります。
交渉して取り返す場合、大半の貸金業者は5~7割程度の返還額を申し出てきます。担当する弁護士の腕次第では回収額を増やせる可能性がありますが、全額を返還してもらうのは厳しいのが実情です。
裁判を起こせば、過払い金全額に加えて5%の利息まで請求することができます。しかし、時間がかかることと、交渉での解決に比べて弁護士費用が高くなることに注意が必要です。
過払い金への対応は業者によってもかなり違いますので、正確な過払い金を計算して、高額であれば訴訟も選択肢に入れつつ、弁護士と対応を検討されることをお勧めします。
また、過払い金請求が数多くなされたことで、武富士のように倒産した消費者金融もあります。最近倒産した企業であれば、債権者としていくらかのお金を受け取れる可能性はありますが、何年も前に倒産した企業の場合は過払い金の回収は不可能と考えてください。
少額の過払い金しか発生しない場合とは
過払い金が発生していても少額で、手間をかけて請求するメリットが低いパターンをご紹介します。
(1)借り入れた日付が新しい
合法的な業者からの2010年6月以降の借り入れに関しては、過払い金が発生していないと考えられます。(※手違いで発生することはありえますが、可能性は非常に低いです)
また、2010年6月以前の借り入れに関しても、貸金業者等は2007年ごろから段階的に利率を引き下げていますので、利率が29%より低くなっている可能性があります。特に、途中で金利の見直しが行われ、高金利での取引期間が短かった場合は、過払い金がわずかしか発生していないケースも考えられます。
とはいえ、過払い金があるということは、その当時は違法な利息を支払って損をしていたことを意味するので、適正な契約だったと考えましょう。
(2)借りた金額が少ない
例えば、10万円程度の借り入れと返済を長年繰り返していても、過払い金の金額は少ないと考えられます。
利息制限法では、借りた金額が少なければ、比較的高い利率を設定することが可能です。借金額が10万円未満の場合は20%まで設定OKなので、出資法の上限である29%との差は9%しかありません。その分、過払い金の発生額も少なくなります。
目安としては、30万円以下の借り入れの場合、長期にわたって返済していても、過払い金が高額にならない可能性があります。
詳しくは、取引履歴を取り寄せて、過払い金を概算されることをお勧めします。
(3)借金を途中で完済している
ボーナスが入った、相続で財産が増えたなどの理由で、分割払いの途中で一括返済をした場合は、支払った利息が少ないため、過払い金が少ない可能性があります。
さらに、途中で完済していた場合、後述する「取引の分断」に当たる可能性があります。
(4)取引の分断があった
長期にわたって借り入れと返済を繰り返していた場合、全体を「一連の取引」と捉えて多くの過払い金を請求できる可能性があります。しかし、返済後数年にわたって新たな借り入れをしていなかったケースや、借金を途中で完済していた場合は、取引が分断されたとされ、受け取れる過払い金が少なくなることがあります。
「一連の取引」や「取引の分断」については、法律的な判断が絡むので、素人では正確な過払い金の算出は困難です。必ず法律の専門家に相談してください。
過払い金返還請求にかかる費用
過払い金請求を弁護士に依頼した場合は、一般的には、以下の費用が発生します。
【弁護士費用の目安】
相談料:無料~1万円程度
過払い金の場合、相談料無料で受け付けている事務所も多いです。
着手金:1社につき、無料~4万円程度
過払い金請求を正式に依頼した時点で支払う費用で、返還請求の結果や金額にかかわらず発生します。着手金は過払い金の調査や計算、債権者との交渉にあてられます。
解決報酬金:1社につき、2万円まで(上限あり)
過払い金請求が完了した後に支払う費用です。日弁連の規定により、1社あたり2万円までと上限が決められています。
過払い金回収報酬:
交渉で和解した場合…過払い金の20%以下
訴訟…過払い金の25%以下
現実に回収できた過払い金の金額に応じて支払う費用で、日弁連の規定で上限が設定されています。和解と訴訟ではこの報酬の割合が異なり、訴訟のほうが報酬の割合が高くなっています。
もっとも、弁護士費用は事務所によってかなり異なるので、ご自身のケースでは具体的にいくらかかるのか、相談の際に尋ねたほうがよいでしょう。
また、過払い金請求の結果は弁護士の腕にも左右されるので、費用だけで選ぶのではなく、実績や評判、実際に会って話してみた印象なども総合的に見て選ばれることをお勧めします。
過払い金請求は弁護士に相談を
過払い金がいくら発生しているか、現在も請求可能か、請求すれば何割返ってくるのか、具体的な弁護士費用などは、弁護士に直接相談されることをお勧めします。
過払い金がいくらになるかは、相手方の企業によって異なります。大手の消費者金融やクレジットカード会社ならば、検索すれば過払い金の発生対象か、現在も回収可能かわかりますが、中小の貸金業者はその限りではありません。
10年前以上の借金なので、金融機関の名前を漠然としか覚えていない、いくら借りたかわからないという場合でも、弁護士に調査を依頼すれば判明するケースがあります。
既に完済した借金で、現在同じ業者に借金がない場合、過払い金を請求することにデメリットはほとんどありません。まずは気軽に調査されることをお勧めします。
この記事の監修者

-
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑