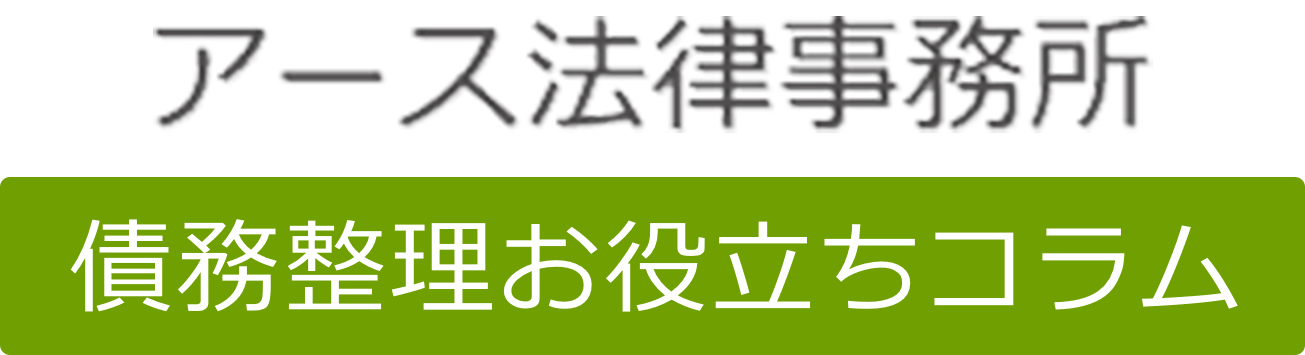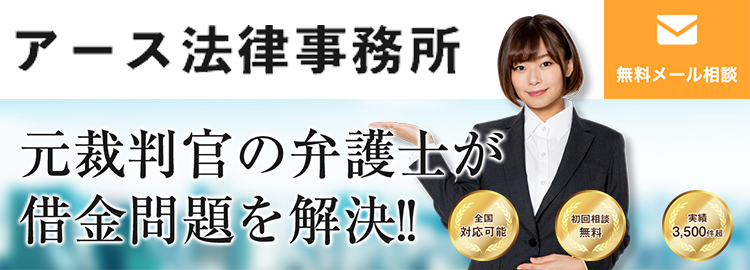任意整理できないケースと対処法
任意整理ができないケースとその場合の対処法について概説します。任意整理は、借金額が大きすぎて3~5年の分割払いで返済できない場合は手続きできません。また、相手方企業が和解に応じない場合や、税金などの債務も任意整理できません。任意整理をするための5つの条件と、任意整理を行ったほうが良いと判断する基準、任意整理以外の借金問題解決法についてまとめました。
任意整理の手続が可能な5つの条件

任意整理ができる条件とは、(1)安定した収入がある、(2)借金の元本を3~5年程度の分割払いで返済できる、(3)債権者が和解に応じてくれる、(4)保証人や抵当権などの担保がついていない借金である、(5)債権者から差し押さえを受けていない、という5つが挙げられます。
以下、詳しく見ていきましょう。
(1)安定した収入がある
任意整理は、債権者と交渉して将来利息をカットし、残りの借金を3~5年程度かけて分割払いする手続きです。そのため、継続的に収入があり、やりくりをすれば一定額を返済に回せる余裕がある人に向いています。
ある程度安定した収入があれば、パートやアルバイトなどの非正規でも任意整理は可能です。また、自営業やフリーランスなどの個人事業主、年金受給者も手続きは可能です。
(2)借金の元本を3~5年程度の分割払いで返済できる
任意整理の場合、借金を大きく減らすことは難しく、また、既に支払った利息も返って来ません。一般的なケースでは、これから支払う利息をカットして、借金の元本を原則3年、長くても5年程度で分割払いしていくことになります。
分割払いの期間は債権者によっても異なりますが、3~5年程度を目安に、毎月払いであれば36回~60回程度で完済できるか計算してみましょう。
(3)債権者が和解に応じてくれる
基本的に、ほとんどの債権者が任意整理の交渉に応じてくれます。
なぜなら、任意整理は借金問題が比較的軽い段階で行う手続きであり、債権者が交渉に応じないと個人再生や自己破産に進むおそれがあるからです。そうなると、債権者としては貸したお金が大幅に減額され、もしくは全く返って来なくなり、裁判所の制度なので逆らうことも難しく、大損をしてしまいます。
将来、大損するくらいなら、今、少しの損でできるだけ返済してもらいたい…と考えるのが一般的なため、話し合いに応じやすいのです。特に、任意整理が得意な弁護士を通じて任意整理をすれば、成功率は高くなります。
しかし、返済実績がほとんどない場合など、一部話し合いを断られるケースがあります。
(4)保証人や抵当権などの担保がついていない借金である
借金に連帯保証人がいたり、所有する不動産に抵当権などの担保権が設定されていたりする場合は、任意整理は難しくなります。
その理由は、債権者としては連帯保証人がいる場合はそちらに全額請求すればよく、担保がある場合はその不動産を競売にかければ全額回収できるので、わざわざ借金減額の話し合いに応じる必要性がないからです。
もっとも、複数の借金がある場合、任意整理は対象の債権者を選べるので、保証人や担保のついている借金を対象外にすれば、他の借金を任意整理することは可能です。
(5)債権者から差し押さえを受けていない
借金の返済が滞り、債権者から既に給与などの財産差し押さえを受けている場合は、任意整理では差し押さえを解除できません。任意整理ができるのは、差し押さえされる前の借金に限ります。
任意整理ができないパターンと対処法
任意整理ができないケースとは、(1)収入がないか、もしくは安定していない、(2)借金額が大きすぎる、(3)債権者が和解に応じないことが予想される、(4)借金や債務の性質が任意整理に適していない、(5)債権者から差し押さえを受けている、という5つが挙げられます。
(1)収入がないか、もしくは安定していない
病気療養中で無職など、収入がない場合は任意整理はできません。また、収入はあっても少なく、家計を切り詰めても借金返済に充てられる余裕がない場合は、同じく任意整理は難しくなります。
このような場合は、裁判所で自己破産の手続きをとることになります。自己破産は収入がなくとも可能で、免責を受けられれば全ての借金は帳消しになります。また、家財道具など生活に必要な品物以外の財産がない場合、「同時廃止」と言って裁判所費用を安くできる可能性があるので、弁護士に相談してください。
(2)借金額が大きすぎる
収入はあっても、借金の金額が大きすぎて3~5年の分割払いではとても支払い切れないという場合は、任意整理は難しいです。この場合、個人再生か自己破産のどちらかを選んで裁判所で手続きをします。
個人再生は、借金総額を5分の1~10分の1程度に大幅に減らせますが、借金額が5,000万円を超える場合は手続きができません。
自己破産は、借金額がどれほど高額であってもゼロにできます。
(3)債権者が和解に応じないことが予想される
任意整理は、債権者との私的な交渉による借金減額手続で、裁判所の手続きのような強制力はないので、ケースによっては話し合いが難しくなります。
【任意整理のハードルが上がるケース】
・まだお金を借りてから半年程度など、取引期間が短い
・すでに裁判を起こされている
・2回目以降の任意整理
・取引や返済中に規約違反があった
・弁護士や司法書士などの専門家を通さないで交渉した
規約違反とは、名義貸しによる借金や、クレジットカードのショッピング枠を現金化したりするなどの行為です。
また、司法書士や弁護士に頼むとお金がかかるからと、自分で交渉しようとすると、法律の素人相手だと足元を見られたり、交渉に応じなかったりするケースがあります。
これらのケースに当てはまらなくとも、相手企業の経営状態が悪い場合には和解条件が厳しくなることがあります。
任意整理の経験豊富な弁護士を通じることで、話し合いに応じやすくなりますが、最初から裁判所を通じた手続きをしたほうがよい場合があります。個人再生か自己破産か、より債務者の状況に適した手続きを選択することになるでしょう。
(4)借金や債務の性質が任意整理に適していない
・税金や社会保険料
税金等は任意整理できませんので、債務者自身が税務署や地方公共団体に赴いて相談する必要があります。納税は国民の義務なので、普通の借金のように交渉して減額することはできません。ただし、状況によっては税金がすぐに全額支払えない人向けの分割払いなどの制度が利用可能です。
税金や社会保険料は、任意整理や自己破産でも減額できないので、返済資金ができた場合は最優先で支払うことをお勧めします。
税金がどうしても支払えない場合は、生活保護を受ければ、税金の支払いが免除されます。
・奨学金や住宅ローン
奨学金や住宅ローンなど元々の利率が低い借金は、任意整理によって将来利息をカットしてもあまり返済額が変わらず、任意整理の効果が薄いと言えます。これらの借金の返済が苦しい場合は、個人再生や自己破産を検討することになるでしょう。
・慰謝料や養育費
離婚して慰謝料や養育費を支払っているケースは、任意整理の対象外です。また、個人再生や自己破産によっても減額することはできません。
ただし、養育費については、元パートナーと話し合って支払額の見直しをすることは可能なので、弁護士に相談してください。
(5)債権者から差し押さえを受けている
借金を長期間滞納していると、債権者が裁判所に訴え、「支払督促」が届きます。この書面の到着から2週間以内に異議を申し立てないと、いつでも強制執行、すなわち財産の差し押さえができるようになります。
できるだけ、支払督促が届く前の段階で弁護士に相談しましょう。遅くとも、支払督促が届いたらすぐに相談されることをお勧めします。
強制執行がされると、給与の場合、手取り額の4分の1を受け取れなくなるほか、勤め先に裁判所から通知がいくため、差し押さえを受けたことがバレてしまいます。
差し押さえを受けていても、個人再生や自己破産の手続きをとれば解除できますが、任意整理で解決はできなくなります。
任意整理できる条件や基準とは
任意整理ができる目安としては、「借金の総額が年収の3分の1程度であること」と言われています。例えば、年収が300万円ならば、借金額は100万円程度までとなります。これより借金額が高額になってしまうと、個人再生や自己破産を検討したほうが良いかもしれません。
もっとも、年収が300万円であっても、病気があって治療費で家計が苦しく返済するゆとりがないケースなどは、任意整理に向かないケースもあります。
詳しくは、法律事務所の無料法律相談で、任意整理が可能かどうかを確認されることをお勧めします。借金の問題については、近年、多くの法律事務所が無料で法律相談を行っています。
任意整理を行ったほうがよいと判断する基準
「複数の金融機関等から借金をしている」「借金を3か月以上滞納している」という場合、早めに弁護士に相談して任意整理を行うことをお勧めします。
(1)複数の金融機関等から借金をしている
複数の金融機関や貸金業者からの借金、特に、借金の返済のために別の金融機関から借金をしている場合は要注意です。これは多重債務といい、繰り返すと利息の支払いもあるため、借金額が雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。
多重債務状態になると個人での解決が難しいため、弁護士に依頼して債務整理を行うことが一般的です。状態が重いと自己破産しかありませんが、早めに弁護士に相談すれば任意整理で解決できる可能性があります。
自己破産は借金をゼロにできる代わり、一定の金額以上の財産を裁判所によって処分されるなどデメリットも大きいため、早めの対応で任意整理を行ったほうが良いでしょう。
(2)借金を3か月以上滞納している
一般的には、借金を3ヶ月以上滞納すると、信用情報機関の記録に事故情報として残ってしまいます。この場合、任意整理をするデメリットがないので、早めに任意整理を行いましょう。
任意整理最大のデメリットは、信用情報機関の記録に事故情報が残り、ブラックリスト入りすることです。
信用情報機関とは、金融機関や貸金業者、クレジットカード会社などが加盟している、個人のお金の貸し借りを記録する機関のことです。新たな借金やクレジットカード作成の申し込みがあった際、金融機関等は信用情報機関の記録をもとに、お金を貸してもいいかどうか審査します。
この信用情報機関にネガティブな情報(事故情報)が載ることを「ブラックリスト入り」と言い、ブラックリスト入りすると一定期間、新たな借金やクレジットカードの作成・利用が難しくなります。任意整理の場合は5年です。
しかし、借金を3か月以上滞納した場合も、信用情報機関の事故情報としてブラックリスト入りします。したがって、既に3ヶ月以上滞納している人は、その後任意整理を行っても、新たな不利益は発生しません。
また、任意整理を正式に弁護士に依頼すると、弁護士は「受任通知」を各債権者に発します。受任通知を受け取った債権者は、以後、債務者に直接の取り立てや連絡をすることができなくなります。督促の通知や電話に悩まされていた人は、以後、心を落ち着けて借金問題に向かい合うことができます。
受任通知は、弁護士を通じて個人再生や自己破産を行う場合も発送しますので、既に郵便物や電話の音に怯える日々を送っている人は、早めに弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
弁護士に任意整理を断られるケース
任意整理できる条件が整っていても、弁護士に任意整理を断られる場合があります。主に「弁護士費用を支払わない」「連絡が取れない」といったケースで、ルールを守っていれば問題ありません。
(1) 弁護士費用を支払わない
任意整理の弁護士費用は、大きくわけて着手金と成功報酬があります。特に、着手金は事件に着手する前に支払うため、いつまでも支払ってくれない依頼者については、弁護士に担当を断られることがあります。
「借金の返済が苦しいのに、弁護士費用まで支払えない」と悩まれている場合、弁護士費用の分割払いに応じている事務所も多いので、法律相談の段階で分割払い可能かどうかについても尋ねておきましょう。
弁護士に依頼すると債権者からの督促が来なくなるので、この間にそれまで借金返済に充てていたお金を弁護士費用に回すことも可能になります。
(2) 連絡が取れない
弁護士から連絡しても電話に出ない、Faxやメールにも応答がないといった場合、担当を断られることがあります。弁護士はあくまでも依頼者の代理人であるため、債権者との交渉内容につき依頼者の意向を確認しなくてはならず、連絡が取れないと手続きが進められないのです。
忙しい場合や急な病気などもあるでしょうが、弁護士が連絡してきた場合は、簡単な返事でもいいので、折り返し返信するように心がけましょう。
この記事の監修者

-
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑