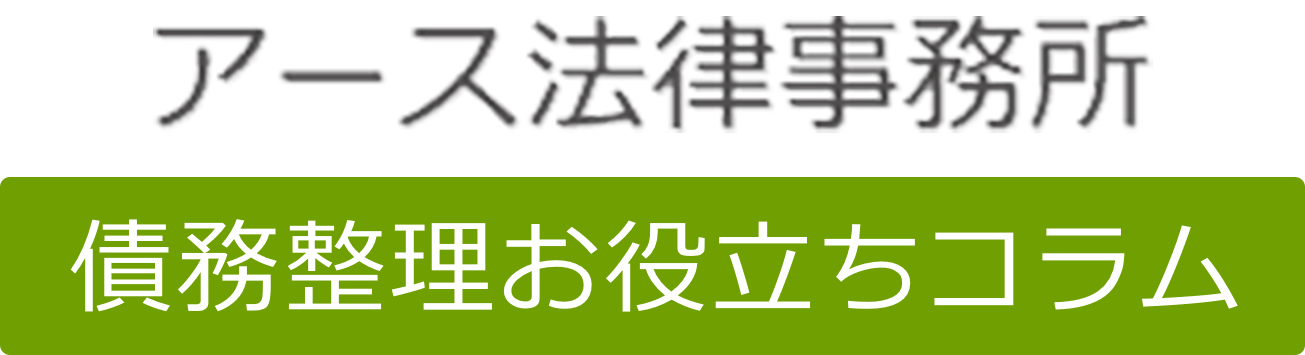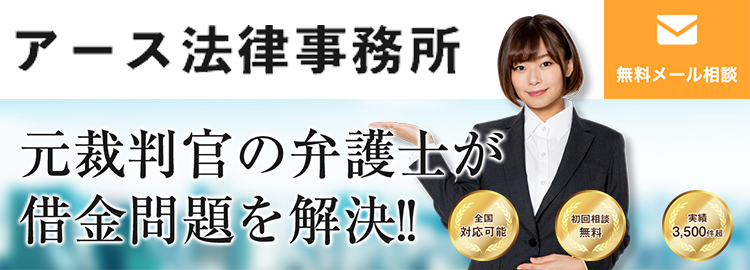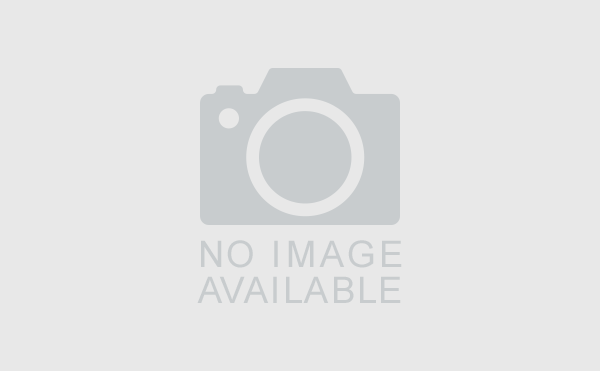自己破産すると選挙権はなくなるのか?
自己破産をしても選挙権や被選挙権を制限されることは一切ありません。自己破産の前後にかかわらず、投票したり、あるいは立候補したりすることも可能です。戸籍やマイナンバーに自己破産の情報が載ったり、パスポートや年金がもらえなくなったりすることもありません。自己破産で本当に制限される権利と、よくある誤解をまとめました。
目次
自己破産しても選挙権は制限されない

自己破産手続を行っても、選挙権が制限されることは一切ありません。
自己破産は借金を抱えた人の懲罰のようなイメージがあるのか、様々な権利制約があると誤解されがちです。例えば、選挙権のほかは、「結婚できない」「年金がもらえない」と言った誤解です。実際は、これらの権利が法律上制限されることは全くありません。
自己破産とはあくまで、借金が自力で返済できなくなってしまった人の生活を再建するための制度です。「こんなに借金をしてはダメだよ」と罰する制度ではないので、合理的に説明できないような制約がつくことはないのです。
確かに、自己破産をすると「破産手続開始決定」が出て、その後、無事に免責が許可されて手続きが終了するまでの間、一部の職業に就く権利などが制限されます。しかし、選挙権は制限される権利ではないので、選挙で自分の票を投じることができます。
なぜ「自己破産すると選挙権が制限される」と誤解された?
自己破産すると選挙権がなくなるという噂が広まった理由の一つとして、かつて、公職選挙法に、禁治産者(成年被後見人)の選挙権をはく奪する規定があり、これが自己破産者と混同されたと考えられます。
禁治産者とは、1999年12月以前に存在した制度で、心神喪失の常況にあって家庭裁判所が財産を治めることを禁じた者(禁治産宣告を受けた者)のことを言います。民法改正により成年後見という制度に変更されました。
公職選挙法11条には、選挙権を有しない者について列挙しています。
公職選挙法11条【選挙権及び被選挙権を有しない者】
第十一条 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一 削除
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
三 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
四 公職にある間に犯した刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十七条から第百九十七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
五 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条の定めるところによる。
このように、法律では、主に犯罪行為で刑に処せられた者を列挙しています。
条文を見ていくと、「一 削除」という項目があります。実は、かつてはここに、禁治産者(成年被後見人)について規定がありました。
しかし、成年被後見人から一律に選挙権を奪うことが問題視され、条文を無効とした裁判例が出たり、日本弁護士連合会からの勧告が行われたりするなどして、当該条文は削除されました。
「自己破産をした者は選挙権が制限される」という誤解は、自己破産者と禁治産者(成年被後見人)が混同されたせいだとも言われています。
しかし、そもそも自己破産者と禁治産者(成年被後見人)は違う制度ですし、誤解のもととなった条文も削除されており、現在は、根も葉もない噂と言っていいでしょう。
被選挙権も制限されない
被選挙権、すなわち、国会議員や都道府県知事、都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員といった職業に就くために選挙に出る権利は、自己破産をしても制限されることはありません。
被選挙権についても、公職選挙法に定めがあります。
公職選挙法10条【被選挙権】
日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
また、被選挙権を失う条件については、選挙権と全く同じで、先程ご紹介した11条に列挙されています。
したがって、自己破産の前後、タイミングを問わず、選挙に立候補することは可能です。
自己破産によって制限されるのは何か?
自己破産によって制限されるのは、主に「一定期間の新たな借り入れ」と「手続き中、一部の職業に就くことができない」という点です。他にも、自己破産手続の種類によっては、手紙を破産管財人に転送されたり、引っ越しや旅行の自由を制限されたりすることがあります。
1. 一定期間の新たな借り入れ
自己破産をすると、約7年間、金融機関等から新たな借り入れをすることが難しくなります。法律にそのような規定があるわけではありませんが、実務上そのようになっています。
日本には「信用情報機関」という、個人のお金の貸し借りを記録し、一定期間保管しておく組織が3つあります。金融機関や貸金業者等は、信用情報機関の履歴をもとに、新たな融資を行うかどうかを決定します。自己破産をすると、その事実が信用情報機関に記録され、一定期間後削除されます。記録が残っている間は、新たな借り入れが難しくなります。
分割払いやクレジットカードも使えなくなるので、不便な点はあるかと思いますが、借金やカードに頼らない生活をする習慣が身につきます。前向きにとらえて、記録が消えるのを待ちましょう。
信用情報機関に自己破産の記録が残っているかどうかは、各機関に履歴開示請求を行うことで確認することができます。※手数料に1,000円程度かかります。
- 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC)
2.手続き中、一部の職業に就くことができない
警備員や生命保険の外交員、宅地建物取引士、建築士など、一部の職業は、自己破産手続の期間中は職業に就くことができなくなります。これは、各職業を規定する法律に定めがあります。
例えば、警備員については、警備業法3条及び14条に規定があります。
【警備業法3条 警備業の要件】
次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
【警備業法14条 警備員の制限】
十八歳未満の者又は第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者は、警備員となつてはならない。
2 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従事させてはならない。
このように、生命保険の外交員であれば保険業法、宅地建物取引士なら宅地建物取引業法に自己破産手続期間中の職業制限が定められています。他には、弁護士、税理士など、主に他人の財産を預かる職業について制限があります。
ご自身の職種が制限職種に当てはまるかどうかは、一度ネットで検索して確かめることをお勧めします。不明な場合は弁護士の無料相談にお問い合わせください。
自己破産手続が終わり、無事に免責が許可されれば、「復権」と言って職業制限も消滅します。破産手続開始決定から免責決定までの期間は、事件の内容にもよりますが、3~4か月程度です。
ご自身の職業が制限対象の場合は、勤め先に申し出て一定期間、他の仕事に配属を変えてもらうことで働き続けることができます。しかし、そうした対応が難しいケースや、個人事業主の場合は、自己破産以外の債務整理も検討したほうが良いでしょう。
3.管財事件となった場合の制限
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。同時廃止は、財産がなく、事件の内容も比較的単純な人向けの手続きです。他方、管財事件とは、主に財産のある人や、自己破産にあたって裁判所が詳しく調査を行う必要があると判断された人が振り分けられます。
管財事件となった場合、以下の制限が発生します。
①手紙を破産管財人に転送される
管財事件となった場合、破産管財人という破産事件のプロが選任され、以降破産管財人が主導して財産の管理・処分や調査などが進められます。破産者あての郵便物は、まず破産管財人に転送され、中身をチェックされたのち破産者に転送されます。
金融機関等からの重要な通知や連絡は郵送で来ることが多く、郵便物から隠し財産や負債などが発覚するケースがあるためです。
②引っ越しや旅行の自由を制限される
引っ越しや旅行をする際には、裁判所の許可が必要になります。旅行は、家族の冠婚葬祭や仕事の都合など、やむを得ない事情があれば認められますが、娯楽のための旅行はNGとなります。
このような制約がつく理由は、破産管財人が破産者の所在を把握し、必要な際にいつでも連絡が取れる状態にしておくためです。
また、借金に困って自己破産したのに、娯楽目的の旅行で散財することは、裁判所にマイナスの印象を与えます。
破産手続が無事に終了し、免責許可が出れば、このような制限は一切なくなります。少しの間我慢して、手続き後の明るい未来と生活を思い描いて待ちましょう。
この他の自己破産による不利益
上記以外の不利益としては、官報に個人情報が掲載されることが挙げられます。しかし、官報掲載の影響は大きくないので、心配する必要はありません。
官報とは、国が発行している広報誌で、法律や条例などを国民に知らせる役割を担っています。自己破産手続をとると、官報に破産した人の住所や氏名などが掲載されます。
これは、金融機関や信販会社、カード会社などの債権者に対し、債務者が自己破産した事実を知らせるためです。
官報は、官報販売所や取り扱い書店で入手できるほか、直近90日分の官報はインターネットで確認できます。
もっとも、一部の職業を除いて、一般人で官報を読んでいる人はほとんどいません。そのため、官報に掲載されたからと言って、自己破産したことが周囲に広まる可能性はほとんどないと言えます。
自己破産にありがちな誤解
自己破産にありがちな誤解としては、「戸籍やマイナンバーに自己破産の情報が載る」「パスポートが発給されない」「年金がもらえない」「会社を解雇される」と言ったことが挙げられます。
1.戸籍やマイナンバーに自己破産の情報が載る
自己破産をしても、その事実が戸籍やマイナンバーカードに記録されることはありません。
確かに、自治体には「破産者名簿」という記録が存在しますが、この名簿に個人情報が掲載されるのは、自己破産手続をしたものの、免責許可が受けられなかった人だけです。無事に免責されれば、この名簿に載る心配はありません。
自治体がこのような名簿を保管しているのは、破産者でないという身分証明書を発行する必要があるからです。
弁護士や公認会計士など、一定の職業は、自己破産手続期間中は仕事をすることができなくなります。そうした職業に就く際、破産者でないという証明書を自治体に発行してもらう必要があるのです。
破産者名簿は非公開で、本人や本人の法定代理人など限られた人のみが身分証を請求することができます。したがって、この名簿から、自己破産した事実が知られることはありません。
2.パスポートが発給されない
自己破産をするとパスポートが発給されないというのは誤解です。自己破産の前後、手続き中を問わず、パスポートを取得することができます。
ただし、手続きの種類が管財事件となった場合、旅行には裁判所の許可が必要です。娯楽での海外旅行は許可されないので、注意してください。
3.年金がもらえない
自己破産をしても、公的年金であれば問題なく受け取れます。確定給付企業年金や確定拠出年金などは自己破産にかかわらず受け取ることができるのでご安心ください。
ただし、個人で保険会社と契約した個人年金は、破産財団に属する財産とされます。
4.会社を解雇される
自己破産をしても、原則として会社を解雇されることはありません。労働契約法16条により、従業員を解雇するためには、客観的に合理的な理由が必要とされています。自己破産は客観的に合理的な理由とはみなされないので、これを理由に解雇することは不当解雇に当たる可能性があります。
【労働契約法16条】
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
もしも、自己破産を理由に会社を解雇された場合は、弁護士にご相談下さい。
この記事の監修者

-
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑