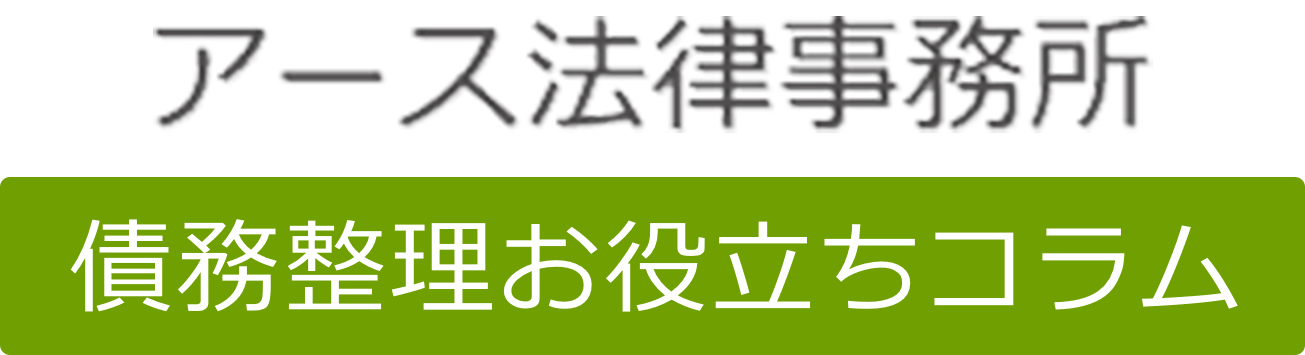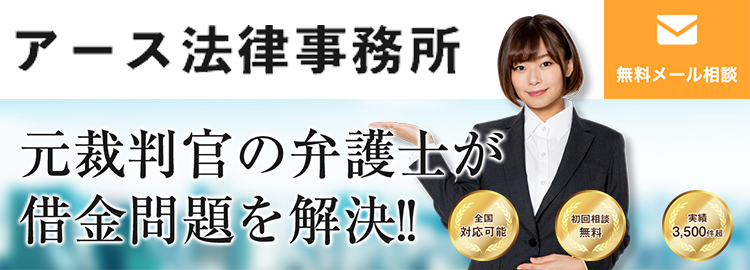自己破産すると税金の支払いはどうなる?
自己破産をしても、税金の支払いは免除されません。市民税・所得税の他、国民年金や国民健康保険料も支払わなくてはなりません。税金を滞納すると財産の差し押さえの可能性があるので、他債権に優先して支払い、支払えない場合は税務署や地方自治体に早めに相談しましょう。自己破産手続と税金の関係についてまとめました。
目次
自己破産しても税金は免除されない

自己破産をしても、基本的に税金は免除されません。市民税や所得税だけではなく、国民年金や国民健康保険料なども免除対象とはなりません。主に税金が苦しくて自己破産を考えている人は、あまり意味がないので注意してください。
これらの国に納める債務は、「非免責債権」と言って、自己破産で免責しても支払い義務が無くならない債権だと法律で定められています。税金は、社会全体のために必要なものであり、法律で帳消しにすることは認められないとされているからです。
例外的に自己破産で滞納税金が無くなるケース
ただし、例外的に、滞納税金が、自己破産手続中に無くなるケースがあります。
土地や建物などの処分すべき財産がある場合に、自己破産手続をすると、「破産管財人」という専門家を裁判所が選任します。破産管財人は、破産者の財産のうち一定額以上のものを処分して債権者に配当します。
税金は、他の債権よりも優先順位が高いので、配当の際に優先して支払われます。その結果、破産者が自分で滞納していた税金を支払わなくてもよくなることがあるのです。
もっとも、これはまとまった額の財産が残っているケースなので、そうでない場合は、自己破産後も税金を支払わなくてはなりません。
税金を滞納すると財産の差し押さえの可能性がある
税金を滞納し続けると、追加の延滞税や延滞金が発生するほか、財産が差し押さえられることがありますので、注意してください。
差押えとは、債務者の財産を債権者が強制的に換価・処分をして、債権を回収することです。通常の債権の場合、裁判所を通した手続きが必要なのですが、税金を滞納した場合は自治体や税務署には裁判所を通さずに差し押さえする権限があるため、通常の借金よりスピーディーに実行されます。
差押えの流れとしては、納付期限から20日程度経ち、相談もない場合は、国税局(所)のコールセンターから、電話がかかってきたり、督促状が届いたりします。
この督促状が届いても無視したまま11日経過すると、税務署や自治体は財産の差し押さえが可能になります。もっとも、実査には財産の調査が行われるため、もう少し時間がかかるでしょう。
財産調査では、金融機関や取引先に対して財産調査を行います。場合によっては、徴収職員が住居や事務所等の捜索を行うこともあります。この時点で家族や勤め先には税金の滞納が分かってしまうでしょう。
それでも納付の意思が認められない場合、財産の差し押さえがなさわれます。差押えの対象は、貴金属などの動産や不動産や現金・預金、給料などです。中でも、現金や預金、給与は換価しなくてもいいので、差し押さえを受けやすい財産です。
差し押さえた財産は取り立てられ、動産や不動産の場合は、入札等による公売が実行されます。売却したお金は滞納国税に充当されます。
給与が差し押さえられても、全額が処分の対象となるわけではありませんが、ただでさえ借金が苦しいのに、受け取れる給与が減ってしまい、非常に困ったことになります。
また、延滞した日数だけ追加の延滞税や延滞金が発生します。延滞税の税率は、国税の場合、期限から2ヶ月までは2.4%、それ以降は8.7%となっています(※令和5年の場合)。仮に国税100万円を1年間納めなかった場合、7.5万円の延滞税を余計に支払うことになります。
参考サイト:国税庁「納税に関する総合案内(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm#a03)」
税金の時効はあるのか?
税金にも時効は存在するので、税務署や自治体が税金の滞納を放置した場合、債務者は一定期間経過後に税金を支払わなくてもよくなります。とはいえ、税務署などが税金の未払いを放置することは通常あり得ないので、税金を時効により免れることは極めて困難です。
税金の時効期間は、税金の種類によっても異なりますが、納付期限から2~5年で時効にかかります。もっとも、未払いの督促状が届いた時点で時効は中断されるため、通常、時効が完成することはまずありません。
大規模災害や戦争などで国の機能が大きく乱れることがあれば、時効が完成することはあり得ますが、そうした事態を待つことは現実的ではないでしょう。
自己破産手続中に税金を支払っても問題ない
税金は他の債権よりも優先度が高い債務なので、自己破産手続中に税金や社会保険料、過去に滞納した税金等を支払っても問題ありません。
自己破産のルールに「偏頗(へんぱ)弁済の禁止」があります。偏頗弁済とは、特定の債権者にだけ優先して債務を返済することで、例えば、「消費者金融からの借金は無視して、勤め先や恩人からの借金を先に返しておく」といった行為が偏頗弁済に当たります。自己破産手続直前や手続中に偏頗弁済をすると、悪質だと判断された場合は、免責が受けられなくなり、自己破産に失敗します。
しかし、税金の納付は偏頗弁済に当たらないので、他の借金を無視して、手続き直前や手続中に返済しても大丈夫です。
むしろ、前述のように滞納税金を放置すると、スピーディーに給与や財産の差し押さえを受けるおそれがありますから、余力があるならば支払っておいた方が良いでしょう。
税金を支払えない場合どうすべきか?
自己破産を弁護士に依頼すると、税金以外の借金などの支払いを一時的にストップすることができるので、その間に滞納税金などを支払うことができます。また、自治体や税務署に相談して分割払いなどの対応をしてもらいましょう。生活がとても苦しく、病気などの事情により収入を増やすことが難しい場合は、生活保護を受けることで税金が免除されることがあります。
1.自己破産を弁護士に依頼する
自己破産を弁護士に依頼すると、受任通知が各債権者に発せられ、以後、債権者は弁護士を通さなければ債務者と連絡が取れなくなります。請求や督促が一時的にストップするので、その間に税金を納めましょう。
また、この期間に自己破産をするための裁判所費用や弁護士費用を積み立てることも可能です。詳しくは、弁護士費用の積立制度を用意している法律事務所に相談してください。
2. 自治体や税務署に相談
差押えがはじまる前に、できるだけ早期に自治体や税務署に相談することで、事情によっては、納税計画の作成などのサポートを受けられるほか、分割納付や1年間の猶予を受けることができます。税金を払う意思があること、現在事情があって支払えないことを正直に伝えましょう。
国税の猶予制度とは、一度に納付することで事業の継続や生活が難しくなる場合や、災害で財産を無くした場合など、特定の事情があるときは、税務署に申請して、原則として1年以内の期間に限って納税が猶予される制度です。
猶予制度については、詳しくは、国税庁のホームページに載っています。
国税を一時に納付できない方のために猶予制度があります(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_04.pdf)
国税の納税の猶予制度に関するFAQ(https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf)
地方自治体の住民税等についても、同様の制度がありますので、まずは自治体の窓口に相談に行きましょう。税金を支払わなかったときのペナルティは迅速かつ強力ですが、皆が払わなければならないものだからこそ、早めの相談で、寛大な対応をとってくれる可能性があります。
3.生活保護を受ける
生活保護を受けていると、所得税や住民税が免除されます。また、滞納している税金については、生活保護を受けた時点で「執行停止」、つまり、請求や督促をされない状態になります。差し押さえを受けることもありません。
これに加え、一定期間生活保護を受けると、滞納している税金の納入義務が消滅します。
国税の場合は3年受給すれば支払わなくてよくなります。
滞納処分の停止については、国税徴収法153条に定めがあります。
【国税徴収法153条 滞納処分の停止の要件等】
税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
二滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
2税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。
3税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。
4第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納処分を行うと滞納者が生活保護を受けなければならなくなる状況を指します。生活保護を既に受けている場合や、生活保護に近い水準で暮らしている場合はこれに当てはまります。
そして、執行停止の状態が3年間継続した場合は、第153条第4項により、滞納税金の支払い義務がなくなります。
参考サイト: 国税庁 第153条関係 滞納処分の停止の要件等(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm)
※生活保護受給のその他のメリット
生活保護を受けると、自己破産に必要な弁護士費用について、法テラスの弁護士費用立替制度が有利な条件で利用できます。
法テラスとは国が設立した法的トラブルのための総合案内所で、法的問題解決を弁護士や司法書士に依頼した場合の費用を法テラスが立て替える制度を用意しています。
立て替えてもらった費用は後に返済しなければなりませんが、生活保護を受けている場合、返済は猶予されます。また、自己破産手続が終了した後も生活保護を引き続き受給している場合は、返済免除の申請が可能です。
また、生活保護を受ければ医療費も免除されるので、怪我や病気で働けない人には強力な制度です。出産費用、義務教育費用、生活のための資格習得の費用、介護サービスや葬祭費用なども免除ないし扶助の対象となります。
生活保護受給には審査があるため、全てのケースで受けられるわけではありませんが、生活に困っている場合は検討されることをお勧めします。
自己破産でも免責されないその他の債権
税金や社会保険料のほかにも、破産法253条1項には、自己破産によって帳消しにならない非免責債権が定められています。「悪意で加えた不法行為の損害賠償請求権」など、裁判所による法的な効力によって免除されるべきではないとされている債権が列挙されています。
【非免責債権】
①租税等の請求権
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意または重大な過失により加えた、人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
④夫婦間の協力や扶助の義務、婚姻費用分担義務、子の監護に関する義務など、家族に関する扶養の義務
⑤雇用していた使用人の請求権、使用人の預り金の返還請求権
⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
⑦罰金等の請求権
まとめ 税金は優先して対応しよう
自己破産をしても税金は免除されませんが、支払えない方への猶予制度などがありますので、まずは地方自治体や税務署に相談されることをお勧めします。
税金を滞納したまま放置すると、普通の借金よりも迅速に差し押さえを受ける可能性がありますので、他の借金に優先して、支払える時に支払ってしまうのが最善策です。自己破産のルール上も、税金を優先弁済することは差支えありません。
生活に困窮して、どうしても税金を支払えない場合は、生活保護受給により執行停止や免除の措置が受けられることがあります。
自己破産をすることで借金が免除になり、その結果、税金が支払える状況になる場合もありますので、まずは一人だけで悩まずに、専門家に相談してください。債務整理の経験豊富な弁護士であれば、ご自身の状況にあったアドバイスが受けられます。
債務整理に関しては、多くの法律事務所が無料での相談に応じていますので、気楽にご相談ください。複数の事務所に相談して、対応が気に入った法律事務所を選んで正式に依頼することも可能です。
この記事の監修者

-
中央大学大学院法学研究科⺠事法専攻博士前期課 程修了
前東京地方裁判所鑑定委員、東京簡易裁判所⺠事 調停委員
東京弁護士会公害環境特別委員会前委員⻑